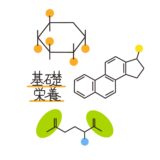ビタミンB1は、尿中にビタミンB1の排泄量が増大し始める摂取量から算定された。
(〇 or ×)

推定平均必要量って、何のための指標だった??
〇
ビタミンB1の推定平均必要量は、尿中にビタミンB1の排泄量が増大し始める摂取量から算定された。
答えは覚えるだけ
答えはマル。
そう、ビタミンB1の推定平均必要量は、尿中排泄量を参考に決められています。
わかります、
この問題「答え」を覚えることは簡単ですが、「そもそもなにを言っているのか?」ここがむずかしいところです。
食事摂取基準とは?
食事摂取基準とは、主に健康な人を対象とした食事のガイドラインです。
「エネルギー」と「栄養素」について載っています。
それぞれ、どれくらい食べればいいか?という値が決められています。
また、栄養素に決められている数字には、『不足の回避』「過剰摂取の回避」「生活習慣病の予防」という3つの視点(目的)があります。
(なんのための数字か?の目的が違う)
栄養素の「不足の回避」について
栄養素の 『不足の回避』を目的とした指標には3つあります。
- 「推定平均必要量」
- 「推奨量」
- 「目安量」
(目的は同じだけど、それぞれちょっと意味が違う。)
つまり今回の問題は、「ビタミンB1という栄養素」の「推定平均必要量(不足回避のための数字)」は、どんな根拠をもとに決めていますか?という質問です。
「欠乏症」ではない。
このとき「推定平均必要量 = 不足回避」なら、ビタミンB1の場合は「欠乏症である脚気の予防」を根拠に決めているんじゃないの??
と考えるのは良い間違え方です。
ゼロから考えればそうなるのですが、「でも実は違うんだよ、知ってた?」というのが今回の問題。
(脚気!って言って間違えてほしそうな雰囲気をしている。)
答えの通り、B1は、尿中排泄量が増大する量が根拠です。
尿中排泄量である理由
B1が尿から出てくるといことは、もう体内量は充分だよ、という合図になっています。
ということは、「尿中排泄量が増大し始める」くらい食べれば、不足は回避しているはず。そんな考え方です。
(欠乏症が出るぎりぎりではなく、もっと余裕をもったラインで、不足回避の量を設定している。B1は体内量が充分になれば尿から出てくるので、その合図がわかりやすい。)
もちろん栄養素によっては、「欠乏症」を根拠に「推定平均必要量」を設定しているものもあります。
でも今回のビタミンB1は違う。
この「例外的なポジションだな」という感覚をつかむことがポイントです(^^
marcy